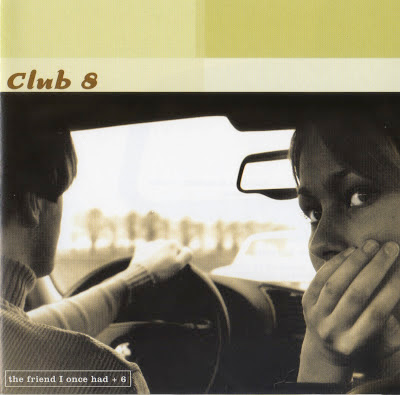初期のロキシー・ミュージックが好き!もし私が何らかの音楽活動をしている人間だったなら、初期のロキシー・ミュージックは理想的な超憧れのバンドになっていただろうと思う。プログレともグラムともつかない、毛色の変わったへんてこなバンド。私が惹き付けられるのは、デビューアルバムから3rdまでの混沌としたサウンドと不気味なヴィジュアル。しかしそれらはすべて計算し尽くされたもの。アイディアとセンスさえあればやっていけるというスタンス、音楽的な知識や技術は二の次(これは2ndまで在籍していたイーノさんの影響があってのことのように思う)、ほとんどのメンバーが美術学校出身のアート野郎集団でもあった。
ぱっと見た限りではどうも老け顔で化粧も誰一人として似合っておらず、コミックバンドな出立ちにぎょっとするけれど(これもハゲなのにロン毛なのか?ロン毛なのにハゲなのか?美形で可愛らしいお顔をしていながら超ケバい化粧を施したイーノさんの強烈なヴィジュアルが一要因)、フェリーさんをはじめ長身で、よく見りゃみんなハンサムなのだ。
初めて聴いたのは「More Than This」だった。洋楽を聴き始めた10代の頃。当然のことながらリアルタイムではないし、しかもレンタルで借りた80年代洋楽のコンピレーションアルバムか何かに収録されていたものだった。他にはオリビア・ニュートンジョンが入っていたような気がするけれど、繰り返し聴いた記憶はほとんどなく、当時は大人っぽい曲で親しめなかったのだと思う。
にもかかわらず鮮明に覚えているのがロキシーというバンド名だった。イギリスの映画館の名前だと後々知るが、私の世代はロキシーといえば90年代後半に女子中高生のあいだで流行したアパレルブランドのROXYがあった。おそらく両者に関連性はないのでどうでもいい与太話だけれど、そのおかげでロキシー・ミュージックという名前だけはずっと覚えていた。
真剣に聴き始めたのはそれから数年後のこと。イーノさんの歌モノのソロを聴いて仰天し、さらには優しそうな可愛らしいお顔で大好きになり(超単純!だけど、密かにロック界一の美形だと思っている!冒頭からイーノさんイーノさんと気持ち悪いですが、普段からずっとイーノさんと呼んでいるのでそのままでいきます)、そのイーノさんがロキシー・ミュージックのメンバーだったことを知る。でも、ロキシーってあの「More Than This」の?とあまりのサウンドの違いに驚いたけれど、完全にミーハー心からイーノさんが参加した1st、2ndを買った。
洗練された「More Than This」を出したバンドとは思えぬ歪なサウンド。比較的ポップな曲はすんなり入っていけたのだけれど、特有のループ構成はどこか退屈で、ロキシーはずっと取っ付き難いバンドだった。そんな私がRoxy Musicを心底好きになったのは彼らの動いている姿を見てからだ。嗚呼、これほどYouTubeに感謝したことはない!このクールなのかダサイのかよくわからないエキセントリックなコスチュームと、奇妙なパフォーマンス、テキトーに見える演奏(もちろん個々の演奏能力はそれほど低いわけではないと思うのだけど、本気で全員ヘタクソだったのか?)、捉えどころのないアヴァンギャルドなサウンド、作り込まれたダサさ、ちょっとスカした感じ。
「Re-Make/Re-Model」(1972年)のソロパートの部分が好き!メンバー全員が強烈な個性!初期のロキシーは個々の自由度が高いバンドだったのだ。上の動画のパフォーマンスではおそらくサックスから唾が逆流しているであろうコスチュームがどう見てもゴーヤなマッケイさん(超クール!)、髭もじゃで最年少とは思えぬ風貌のマンザネラさんのノイジーなギター、なぜか弾まない異様に硬いトンプソンさんのドラム、ピーッビャーッビュルルルルービーッ!なんだかよくわからない発信音みたいなシンセサイザー担当の孔雀羽根の男イーノさん、当時を知らない私にしてみればダンディズム云々と言われても怪しい笑顔のおっさんでしかないフェリーさん。この時点ではまだロキシーは完全にフェリーさんのバンドという感じではないし、イーノさんのバンドでもない。見方によってはマッケイさんのバンドなのかもしれない。
それにしてもロキシーって本当にハンサムなメンバーばかり。フェリーさんはもちろんだけれど、サポートメンバーだったベースのケントンさんの女性的なルックスと控え目な佇まいも好き。というかケントンさんが一番お洒落じゃない?
しかしイーノさん経由でたどりついたのに、ロキシーとなると途端にマッケイさんを贔屓にしてしまう私はただただミーハーな人間なのでした...。
EMIミュージック・ジャパン (2007-09-26)